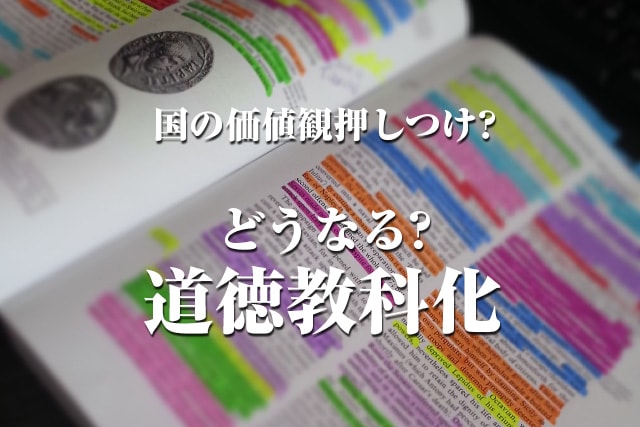かの哲学者ソクラテスは「無知の知」という概念を生み出し、「自分自身の無知を自覚するという時点で相手よりも優れているのだ」と説いた。だが、今の日本には自分自身の“無知”にすら気づけない人たちが多すぎやしないか。こんな状態で選挙権を18歳以上にしても、かえって投票所に閑古鳥が鳴きっぱなしにはならないか。
リベラル最後の“希望”
2015年ほど政治が注目された年はないだろう。
9月の安全保障関連法案強行採決、橋下徹率いる『維新』の躍進、中国軍による南シナ海制圧、東京オリンピックのゴタゴタ…。
その中でも世間の注目を集めたのは、大学生を中心とする政治団体『SEALDs』の登場であろう。
彼らは代表を置かず、完全なる個々人の集まりであることを標榜し、安保関連法案反対を中心に国会前でデモ活動を繰り広げてきた。そう、55年前の日米安保法案に対する岸信介首相(当時)への「アンポハンターイ」と同じように。『SEALDs』は、基本的にリベラル寄りの団体である。
そのメンバーは東京のみならず地方出身者も数多く存在しており、中でも沖縄出身者に多くのスポットライトを浴びせているようだ。
「世界一危険な基地」と言われるアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設問題を抱えているだけに、「日米の権力者に虐げられている沖縄県民」というイメージを打ち出したいリベラル勢力としては、若い同志の登場は何より心強かったはずだ。
教育現場の怠慢
しかし、彼らの活躍もむなしく、安倍政権の支持率は、危険水域と言われる30%台をなかなか割り込まない。不支持率が支持率を上回っている状況ではあるものの、“反安倍”が世間のムーブメントとなっているかといえばそうでもないというのが現実であろう。
その背景には、『SEALDs』をはじめとするリベラル勢力が戦後70年間(もっと言うと日本に共産主義が入ってきてから)、ずっと同じ主張を繰り返してきたという過ちがある。悪い言い方をすれば、リベラルは進歩していないのだ。
振り返ってみれば、日本における政治活動は労働組合や業界団体といった圧力団体と呼ばれる組織が主として行っており、個々の日本人は何も政治的なことを考えなくても十分生活できた。
教育の現場では、文学や歴史といった過去の出来事に学ぶことを重視する傾向が根強く残っているものの、政治や社会問題の話になると、変な共産主義思想に染まった教師が前時代的でトンチンカンな思想を振りかざしたり、とにかく異論を認めない状態が長く続いてきた。そんな閉鎖的な教育環境で育ってきた子どもたちが、果たして左右両方の主張に耳を傾けるような人間に育つであろうか?
ガラパゴスから脱却するために
この状況を打破するには、まずリベラルが過去の過ちを反省する必要がある。
「世界平和を唱えているだけでは、テロリストはいなくならない」「人類が存在している限り、争いはなくならない」「多少嫌な気持ちになっても、自分と対立する人の意見に耳を傾けなくてはならない」…。
左右双方が己の感情だけをぶつけ合うだけでは、いつまで経っても建設的な議論は生まれない。そして、子どもたちはそういった光景を“醜悪”なものとして見つめるはずだ。
大人気ない大人にならないためにも、まず日本人一人ひとりが正しいディベートの仕方を学ぶ必要がある。
例として、欧米のテレビ討論番組では、「賛成」「反対」ともう一つ、「中立」的な意見を持つ人を必ず登場させる。その中立派が賛成・反対双方に率直な疑問をぶつけることで、議論を活性化させ、落としどころを上手く探っていこうとするのだ。
日本でもそういう教育方法を実行すれば、自然と投票率のアップにつながっていく。
人間は、二者択一で成り立っている生き物ではない。様々な意見や主張を持っている人が多くいるからこそ、世界は巧みに回っているのだ。
自分たちの理想に固執するあまり、世界の現実に見て見ぬ振りをし続けてきた結果、日本人の政治的無知があちこちで露呈し、「日本はガラパゴス」だと世界中から生温かい視線を送られる。
これからもその路線で行くというのなら、別に止めはしない。ただし、その論法で世界を相手にしても絶対に勝ち続けるという確証があればの話だが。