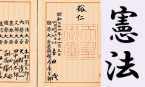7月21日は、参議院議員選挙です。選挙権のある方はぜひ投票に行きましょう。もし、「どこに投票したらよいか分からない」という方は、当サイト「政くらべ」の政策比較やボートマッチを試してみてください。
※この記事は2017年3月に公開されたものを加筆修正したものです。
「貴重な休日に投票に行きたくない」という有権者の本音

7月21日に投開票が行われる、今回の参議院選挙は梅雨の真っただ中の選挙です。雨の日は投票率が伸びないと言われます。確かに、雨であったり寒かったりしたら、家から出て投票所まで行くのはおっくうかもしれません。しかし、好天に恵まれ暖かな日曜日だったら、レジャーに出かけたいと思いませんか? そう、天気がよくても投票率はのびないのです。
お子さんのいる家庭であれば、家族で出かけられる貴重な休日です。お子さんのイベントもたくさんあります。独身であれば、土日のどちらかは、たまった洗濯物を洗って、部屋を掃除してといった家事に1日を費やし、もう1日は趣味に使うという方が多いのではないでしょうか?
近年の選挙の投票率は右肩下がりです。特に、20代~40代にかけての働き盛り、子育て世代の投票率が低いのは、日曜日が投票日だからというのは要因のひとつとして考えられるでしょう。
そもそも投票日が1日だけという現行の選挙制度でよいのか、投票期間を長くすればよいのではという意見もあります。また、ネット投票をできるようにするべきだという声もあります。ただ、実際に選挙制度の抜本改革となれば、そう簡単に事が進まないのが今の日本です。
でも、現行の制度のなかでも日曜日にわざわざ投票所に行かなくてもよい方法があります。
期日前投票です。
期日前投票をすれば、堂々と投票日に遊びに行ける
私は千葉県民ですが、2017年の県知事選挙は日曜日に予定があったので、期日前投票をしました。
期日前投票は、選挙当日に予定があって投票に行けない人が事前に投票に行ける制度です。投票に行けない理由は、仕事や冠婚葬祭などやむ得ない事情というわけではなく、旅行やレジャーであってもかまいません。
最近では、ショッピングセンターなどにも期日前投票所が設置されていたり、駅の近くに期日前投票所があったりするので、買い物ついでや仕事帰りに気軽に投票できるのです。投票方法も、投票日の投票方法と同じで、投票用紙に記入して投票箱に入れるだけ。
「投票日に投票しなきゃ選挙じゃない!」なんて思わないで、期日前投票を活用しましょう。
期日前投票と不在者投票はどう違うの?
期日前投票のほかに、不在者投票というのもあります。そもそも、この2つは何が違うのでしょうか?
期日前投票とは
投票日に投票できない人が、選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票のことです。選挙人名簿登録地とは、基本的に住民票のあるところです。つまり自分の住んでいる市区町村の期日前投票所で投票するのが期日前投票です。
例えば千葉県船橋市に住んでいる人が、仕事やショッピングの帰りに、浦安市や市川市の投票所で期日前投票することはできません。でも、船橋市内であればどの投票所でも期日前投票ができます。投票日は自宅近くの投票所に行くのが原則ですから、そういう意味でも期日前投票はとても気軽に投票できると言えます。
不在者投票とは
投票日に選挙人名簿登録地以外の場所に滞在している場合、その滞在先の選挙管理委員会で投票できる仕組みのことです。
例えば、千葉県在住の人が、会社の研修で1ヵ月間福岡に滞在していて、その間に選挙がある場合、福岡で千葉の選挙の投票ができます。また、病院や介護施設などに入院している人は、その施設内で不在者投票ができます(指定の施設に限る)。
さらに、障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている方や、要介護5の方は、郵便での不在者投票が可能です。そのほか、洋上投票や南極投票といったFAXを使った不在者投票もあります(国政選挙のみ)。
寮に住む学生は不在者投票が認められない!?
不在者投票を利用すれば、住民票のない場所にいても投票ができるわけですが、学生などで、住民票を実家に残したまま寮生活を送っている人は注意しなければなりません。
自治体によっては、「居住実態がない」と判断され、住民票があっても選挙人名簿に登録されないということがあるからです。
参考:「16年参院選 不在者投票、学生1773人できず」毎日新聞
総務省は「住民票を移して転居先で投票するのが原則」としています。実家から離れて寮生活などを送っていれば、居住実態は寮にあるので、「不在者投票」とはちょっと違う気がします。たしかに、住んでいない地域の、例えば市議会議員や市長の選挙を別の地域に住んでいる人が選ぶというのはおかしな気もします。
しかし、一方で大学生などが実家を離れて暮らすのは、学校に通うために学校の近くに住む必要があるわけであり、住んでいる期間は学校に通っている間だけです。大学でいえば、4年ですし、短大や専門学校であればもっと短い期間です。
その間に地方議員や首長を選挙で選んでも、政策が実施されるのはもう少し先の話になります。都合よく1年生のときに選挙があれば、在学中に選挙で選んだ人の政策が実現するかもしれませんが、4年生の3月に選挙があったら、その地域のことを考えて選挙に投票に行く必要があるのでしょうか? 2017年の千葉県知事選挙や秋田県知事選挙がまさにそうではありませんか!
若者が流出して高齢化が進む地方においてはなおさらのことです。住民票を残して学生生活を送るということは、卒業したら帰ってくるという可能性もあるのです。であるならば、故郷の選挙の投票権を奪うのはどうなのでしょうか?
また、国政選挙はどうでしょう? 居住実態がないということで、選挙人名簿に登録されないということは、投票する権利がないということです。現在の国政選挙では、衆議院議員選挙でも参議院議員選挙でも比例代表制があり、政党に対する投票もあります。地域性が加味されないわけではありませんが、国のために働く議員を選ぶ選挙ならば、その地域に住んでいないからと言って投票権を与えないというのは、憲法違反である気もします。
参考:「一人暮らしの学生は親元の選挙人名簿から抹消される? 疑われる違憲性」中西又三中央大学名誉教授

なぜ地域差が出るのか? 北秋田市と我孫子市の選挙管理委員会に聞いてみた
「住民票はあるが、居住実態がないので投票権がない」という考え方については個人的には疑問を持ちますが、さまざまな解釈があるので、そういう形で統一されているのならば仕方がないかもしれません。しかし問題は、自治体によって不在者投票ができたり、できなかったりするのは不平等ではないかと思うのです。
なぜそんなことになってしまうのか?
毎日新聞で報道された中で、現在(2017年3月当時)、まさに不在者投票ができない可能性がある秋田県北秋田市の選挙管理委員会に問い合わせてみました。ちなみに北秋田市は2017年は県知事選挙だけでなく、市長選挙(4月2日告示)も行われます。※2017年の北秋田市長選挙は、立候補者が1人であったため無投票となりました。
※投票案内を送る=選挙人名簿に登録する
「住民票はあるのに居住実態のない学生さんに対して選挙ハガキを送らないのはなぜですか?」
――まず、学生さんだけではないです。総務省の見解もあり、また最高裁の判例(※最高裁大法廷判決昭和29年10月20日(茨城大星嶺寮事件)のことと思われる)もあることから、居住実態のない方には投票案内は送らないことにしています。
「居住実態の調査はどのように行っているのですか?」
――選挙権を得た住民の方に郵送で居住実態があるかどうかのハガキを送っています。「居住実態がない」と回答を返送してきた人だけ、投票案内を送らないようにしています。
「返事をくれない人はどうしているのですか? そもそも住んでいないのならば、ハガキの返信はできませんよね?」
――返信してくるのはご家族の方ですね。返事をくれない方に対しては、居住実態が不明ですので、投票案内を送っています。
「返事をしない人のほうは投票権があって、返事をした人は投票権がないのって正直者が馬鹿をみるみたいじゃないですか?」
――そうかもしれませんが、確実に居住実態がないと判断できない場合は、投票案内を送らないわけにはいかないので…。その方に対して、次の選挙でも追跡調査として居住実態調査のハガキを送るようにしています。
北秋田市は真面目にも、選挙権を得た住民一人一人に居住実態調査を行っています。そして、総務省や過去の判例に従って、実態のない人には投票案内を送らないのです。さらに、調査ハガキを真面目に返信して正直に居住実態がないと返事をした人に限って選挙権がなくなるのです。なんてバカ真面目なんだ北秋田市!
一方で、私の地元である我孫子市の選挙管理委員会にも問い合わせてみました。
「我孫子市は居住実態がなくても選挙ハガキを送っているようですが…?」
――居住実態を正確に把握するのは困難なため、実態調査そのものを行っていません。住民票に基づいて、投票案内を送っています。
「そうですよね。正確に把握するのは難しいですよね。調査ハガキを全員に送るコストも馬鹿になりませんよね。でも、本人が直接居住実態がないと言ってきたらどうするんですか?」
――そういうことはいままでなかったので……なんとも言えませんが。住民票に基づいて送ると思います。むしろ、寮に住んでいて不在者投票したいという学生からの問い合わせが最近増えていて、そういう方には不在者投票の申請の仕方などを教えています。
18歳選挙権の影響もあり、学生からの問い合わせが増えているという我孫子市。わざわざ選挙管理委員会に問い合わせて「投票したい」という学生がいるということは、なんだかうれしく思ってしまいます。そして丁寧に教えてあげている我孫子市はなんて親切なんだ!
2つの選管に問い合わせて思ったのは、どちらもきちんと仕事をしているということです。
要は決めの問題です。我孫子市に住民票があり北秋田市に住んでいる人は不在者投票できるけれど、北秋田市に住民票があり(まじめに居住実態がないと回答して)我孫子市に住んでいる人は不在者投票ができないという不公平な問題が実際に起こっています。
この不公平は一刻も早く解決すべきです。
期日前投票・不在者投票をもっと広めるには
ますます低下している投票率を上げるためには、期日前投票・不在者投票をもっと広げるように周知する必要があると思います。
どんどん広げて、得票数の半分ぐらいか期日前投票という日がくれば、投票率は劇的に上がるのではないでしょうか?
それにはまず、立候補者や選挙管理委員会は情報を早く出すことです。
期日前投票は、選挙告示日の翌日から投票可能です。ところが、告示日には選挙公報はまだ配られていないし、政見放送もされていません。国政選挙では、各政党の選挙公約が出来上がるのは、告示日の直前です期日前投票がスタートするときには、しっかりと有権者が判断できる材料は整えておくべきです。
なにはともあれ、皆さん!投票に行きましょう!